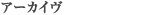比嘉良治(1938年~)
沖縄県名護市生まれ。名護高校で美術クラブに所属。多摩美術大学洋画科卒業後、渡米。コロンビア大学修士課程を卒業。ロングアイランド大学名誉教授。ニューヨーク在住。最初は絵画、版画の抽象的作品であったが、写真作品を中心に制作するようになる。1987年より名護市主催の「フォトシンポジウムin沖縄」(名護写真まつり)のコーディネーターを20年近く続けるなど、沖縄と国内外を結ぶ役割を続ける。2010年頃から積極的に沖縄に関わるようになり、県内中高校などでワークショップを行っている。
収録日:2012年2月25日
収録場所:沖縄県立博物館・美術館屋外展示場民家(那覇市)
聞き手:町田恵美 撮影:大山健治
書き起こし:大山健治
町田:現在も活動を続けていらっしゃいますが、作家を志したきっかけを教えてもらえますか?
比嘉:はい、僕は名護で小学校まで裸足で生活していた時代に育ちました。で、勉強も働く(農作業)も嫌だし、怠け者だった。でも何かをしなきゃと思ってたのでしょう。そんなとき翁長先生と出会った。先生がみんなに「君達には、何か誰よりも優れたところがある。それを見つけろ」と言われて、そのときに凄く悩んだのね。僕が他人より秀でているのは何だろうって。みんな勉強するか仕事をしてるし運動はできるし……。悩んだ末、やっぱり絵かなと。その頃、絵の先生がいなかったんですよ。中学も絵の先生がいなくて、同級生に一人凄く絵のうまい人(照屋寛君)がいた、彼と六年生の放課後、毎日学校に残って絵を描いていた。放課後残ったもう一つの理由は、たぶん家に帰ると仕事が待っていることと勉強をしなければいけなかったからだと思う。まあ中学のときは迷いがあってね、生物系に行こうかなと思っていた。草木を集めたりいろんな観察が好きだったが、結局、受験を控えた中学三年のとき試験の点数が急降下してきて他の進路の選択肢が狭まっていた。やっぱり俺は絵で行こうと、画家になることを決めてました。高校に入って初めて絵の先生に恵まれて、先生はニシムイの画家達と一緒に戦前、東京で絵を学んだ仲間の一人だった。もともと首里の人で名護に移ってきたらしい。古波蔵誠仁という先生で僕にとって初めて出会った画家だった。
厳しい反面、優しく我々を非常に可愛がってくれた。画材の手解き、絵画とは、現代絵画、画壇のこと、厳しい芸術家の人生などなど贅沢なほどいろんなことを教えてくれて、どうしても東京の美術大学に行きたいと夢が膨らんだのも古波蔵先生のお陰ですよ。中学の三年のときに、今でいう学校の進路指導っていうのですか、親の希望を聴く項目があって、親父は細菌学をやれと。当時、細菌学なんて耳にしたことがない言葉でしたから、学校の先生もビックリしたでしょう。でも、あくまで親の希望であって、お前がやりたいことは何でもいいと。お袋は絵描きだけにはなるなと。あの頃はちょうど反抗期だったのか「どうして?」と聞いたら絵描きは貧乏だからと答えた。じゃあ、貧乏覚悟したらいいと言う事だなと(笑)。それで絵描きを志望したんだけど親に啖呵を切った手前、責任があるから親には負担はかけない覚悟をした。東京の大学に行ったのもそういった気持ちがありましたので。まあ絵描きに成るきっかけは他にやれることが無かったことも事実で、ほんとに何もとりえが無くて……。
町田:大学は多摩美術大学に行かれるんですけど、その頃の事について……。
比嘉:その頃はね、戦後間もない頃で、私費留学の枠が広がって、多摩美が4年制になって間もない頃でした。何故多摩美に行ったかというと、4年生の大学で高校の教師の免許が得られることと自由な校風だったのと。親に自分で生きていくって言った手前、先生をしながら絵が描けたらいいなと、多摩美に行きました。あとは友達からの情報を得て。僕が行ったときは、沖縄から4番目だったんですよ。嘉手川(繁夫)さんが初めてで、その次が与儀(達治)さんがいて、那覇出身の真喜屋さんがいて僕が入った。その後、真喜志(勉)でその後次々入ってね。当時は多摩美でパスポートを持った留学生でわりと目立っていました。でも、先輩達が非常に熱心に絵を描いて、凄く良い影響を受けたし、当時の沖縄から意を決して来たと思うんですよ。だから、学校もアルバイトも一生懸命やっていた人達で……。よく言われるんです、多摩美の売店の人や事務の人なんかに「誰それ先輩は良かったのに」なんてね(笑)。そういう多摩美時代でしたね。若手の美術評論家が沢山いたし、新しい造形教育で熱気が溢れていました。ニューヨークから東京の個展のために一時帰国した川端実や岡田健三教授らが多摩美で講演して、生の風に興奮しました。ちょうどニューヨークに興味持っていたんで、自由が丘の岡田先生の家に訪ねて「実はアメリカに行きたいんです」と自分の作品を持って行ったんです。そしたら「この絵だったら来てもいいだろう」と「その代わり死ぬ覚悟で来いよ」と言われました。「わかりました」と言って別れたんですけど。ニューヨークに行っても川端実さんには会ったけれども、岡田健三さんにはそう言われた手前、実力が付いてからお会いしようと思い、でもついにお会いできませんでした。お亡くなりになって。僕は、沖縄から――貧しい時代ですから――東京で4年間アルバイトしながら大学を卒業できるとは思ってなかったんです。中退も考えたんです。でもまあ何とか卒業して、東京の中学高校と教えたんですけど、本当は高校の講師になりたかったんです。絵を描く時間の余裕が欲しくてね。ところが下宿近くの学校で専任の先生を探してたんですね。その学校になんとか講師でとお願いしたけれど、どうしても専任になってくれと言われてました。そのかわり給料が安いので週一日研究の休みがあるという。休みの方が魅力で妥協して職を得た。すると、なんとか生活が出来るようになった。現代展なんかに入ったり、個展を開いて一行でも美術雑誌に評が出たりするようになっていた。僕はこれは危険な状態だなと思ってね。 24、5才で生活基盤が整い、絵描きとしての活動が見えてきた。安定、これは崩さないといけないと。安定するのは好きじゃないんです。不安定の状態が一番美しいと僕自身は思っているんですね。そういった状況は壊さなきゃいけないと。じゃあどうしようと考えました。イタリアの美術とかフランスのアンフォルメルとかいろんな現代絵画が東京に入って来ました。同時に、アメリカの現代美術が沢山東京で見ることができた。「ニューヨークだ!」とニューヨークに行ったんです。
当時アメリカは60年代で非常に面白い時代で、今も面白いですよ。ニューヨークは今、不景気だから増々面白くなります。大切な時期だなと思います。絶えず変化する可能性がアメリカ社会にはあります。反して日本の美術はわりと安定した思想というのが底辺にあるんじゃないかというような気がします。変化、激動……。アメリカの美術界では有名になっても作品が悪くなったらポンと落ちますからね。野球でもなんでも同じなんだけれども、それがアメリカ社会の好きな面ですよね。緊張感がありますね。日本の場合、一度有名になったらなんとなく先生としてずっといけるけど、向こうはそうじゃないです。そういう緊張感というのは僕は好きですね。
町田:アメリカでの生活などは。
比嘉:アメリカ行った当時はね、僕だけでなくみんな大変でしたよね。学生のビザで行ったので働く許可を貰い、時間も週に20時間と制限されていました。われわれはビザとか労働基準とか全く知らないで「行きゃなんとかなるだろう」と行ったんですね。今はだんだんビザが厳しくなってます。当時、「読売アンデパンダン」があって、そこで活躍していた連中も沢山来たんで、わりと元気のいい同世代の人が沢山いました。お互いに協力したり刺激しあったりしていい時代だったと思いますね。今はむしろ個人個人で来てる人が多いんで、お互いに何やってるか分からないというのはありますけどね。そういう状態でアメリカに行って、まだ生きてますね。良く聞かれるんですよ。「どうしてアメリカに行ったの」と。まあ、日本で食えないからアメリカで食っているようなもんでしょう(笑)。
町田:絵画だけじゃなく写真や彫刻も手がけていらっしゃいますが……。
比嘉:いや、やりたいものは何でもやっていいんじゃないですかね(笑)。その点、向こうのほうが自由なんですね。ヨーロッパもそうです。最近は日本も変わってますけど、当事は「何で絵描きが写真やるの?」とかね。ピカソはなんでもやってるし「これがやりたい」と思ったらやる。僕は、向こう(アメリカ)に行って写真を始めて……。正式に学んだことは一回も無いんですよ。図々しく大学で教えてるけど(笑)。だから普通の教え方にとらわれず教えやすいという面もあるんですね。
僕はアメリカ行ってすぐバイトをしなければ食えなかった。多くの日本の作家はレストランの調理場で働くか大工をするかでした。調理場っていうと当時ね、僕には暗いイメージがあったんですよ。それよりも空間で働く大工がいいかなと思う気軽さで大工を選んだ。ところが相棒が仕事現場で移民局に捕まって強制送還されたんです。で、地元の小さなところで捕まらないように働きたいと思っていた矢先、美術学校の先生の紹介で、凄くいい額縁屋さんで働くようになった。ニューヨーク近代美術館とかメトロポリタン、ホイットニー美術館など出張で額装を地下の収蔵庫で作業とか、現代作家の額装が主でした。額装だけではなくいろいろ勉強になりました。近代美術館の仕事でたまたまウォーカー・エヴァンズという人の写真を見て、もうショックだったんです。「一枚の写真でこれだけ力強い表現ができるんだ」小さい写真なんだけど感動でした。僕も写真をやってみようと、友達やらいろんな人に見聞きし、森永純さんというユージン・スミスのアシスタントで向こうで働いていた方が日本に帰るときに、引き伸ばし機を譲ってもらって、家に暗室を作ってやって……。それと、行ってすぐ版画を沢山制作していたんです。一点の作品も大切だけど版画の複数性に日本にいるときから興味を持っていたんですね。それでむこうで版画をやっていたんです。それに版画はいろんなコンクールに出しやすいですよね。絵は自分で作品を持っていける範囲でしか応募が可能じゃないですか。送料は高いし。版画が送りやすい。それで版画のコンクールに応募して結構賞を貰ったりしたんです。
ニューヨークに行って2、3年してから大学で展覧会やってくれと頼まれて、展覧会を開いた結果、大学が興味を示してくれまして「うちの大学で教えてくれないか」と言われ、大学しかもアメリカの?という、戸惑いもありましたが教えるのは好きだったんで、教えることになったんです。新たなチャレンジが始まりました。ところが幸いなことに小さな大学の美術学科で非常勤講師でした。ですから毎学期違う科目を受け持つように言われたんです。最初はデッサンのクラスでしたが、絵画、デザイン、版画と。版画もシルクスクリーン、次の学期には石版、次は銅版といった具合に、絵では食えなかったし教えることが好きだったので「じゃあ、やります」と言い、教える一学期前は猛勉強して新しい版種を身につけました。当時、向こうでは石版なら石版で長く時間をかけないと技術的に覚えられないんで、ほとんどの人が一つの版種しか出来なかった。こっちはお陰でいろんな版種をこなせるようになっていた。しかし、やがて教えることに疑問を持ちだしたんです。いや教え方ですね。自分の教え方がほんとにいいんだろうかと。コロンビア大学美術学部で教授たちの教え方を学びたいと思い、大学院に入ったんです。よりいい教育法が学びたかった。自分の教え方は間違ってなかったんだと。自己再確認で自信がもてました。それともうひとつの理由はコロンビア大学で教鞭をとられていた内間安瑆さんに木版画を学びたかったんです。内間さんとは前から親しくしていただいていました。木版画の技術だけではなく道具や素材についても沢山学びましたね。さらに教えないで学ばせる方法などもね。
町田:何かエピソードとかありますか?
比嘉:エピソードはね、内間先生がね、何も言わないんですよ(笑)。大学の木版画のクラスの初日に、ほとんどの学生が彫刻刀など使ったことが無いので、はじめは使い方をちょっとだけ教えるんです。僕が日本の中学で教えてたときの経験ですが、こうやっちゃだめだとか、ここはこう使わなきゃだめだ、という教え方は嫌いなんですよ。自分が修理の方法を教えることが出来る限界まで、生徒に何も言わず道具を壊させてもいいという考えなのです。彫刻刀の研ぎ方を教えることが出来る範囲内までは彫刻刀を壊しても良いというつもりでね。全く自由にさせて壊れたら「修理を教え、何故壊れたか、どうしたら使いやすいか」という教え方が好きなんです。内間さんもね、ちょっとだけ教えるんですよ。あとはにこにこしながら、生徒全員を見て把握している。僕が制作してるそばに来ても殆ど何にも言わないんですよ。僕は未熟で知らないでしょ。一生懸命やって何回も失敗するんですよ。そしたら、しばらくして、あるいは次の週にふっとそばに来て「これをこうしてみては」「これを使ってみては」とおっしゃる。一応、自分流にやらせる。上手くいかないから先生の言葉に「あっそうか、なるほど」と気付く。そういう教え方がね、忘れないんですよ。最初から「こうしなさい。こうしてはいけない」とか言われたら忘れるじゃないですか。何回か失敗するまで忍耐強く待っている。素晴らしい教え方ですよね。そういうエピソードが幾つもあって非常に勉強になりました。それと、自分の絵で表現するときの迷いや解決策などをちらちらっと教えてもらいました。当時どれくらい年齢差があったかわからないけれども、僕はまだ 30代ですからね。最初に会った時から同等に接してくれました。
町田:今後はどのような活動を。やりたいこととか。
比嘉:そうですね、やりたいこと、遊びたいですね(笑)。ひとつは、自分のやりたいこと(制作)と、もうひとつは、やっぱり沖縄人ですから、実際には今 74歳で、沖縄で過ごしたのは7、8年しかいないんですよ。でも一番自分の根底にある沖縄との関わりを意識した場合に、政治状況、戦後からずっと続いてきた基地というのは小さいときから敏感に肌で感じていた。ところが大学行くときには美意識だけで、ニューヨークに行くときも社会情勢よりも芸術意識が強かった。今、沖縄との社会状況や心を大切にして、それをじゃあ、どうやって表現できるかということを写真で思考錯誤しているんです。ひとつのテーマとしては沖縄をどのように撮るかですね。だからまだまだ解決出来ないし、満足した作品は出来ないですね。
町田:20年位前に写真のシンポジウムをなさっていますよね。
比嘉:今、シンポジウムの話がでたんですが、そもそもの経緯からいいますと僕が始めて大学に行ったときに、那覇から東京まで船で行ったんです。東京の多摩川べりに立って「うわあ、こんなに肥えた土、うらやましいな」が第一印象でした。名護は砂地でほんとに何も(作物が)出来ないような土地ですからね。 あと初めて東海道を電車で通過したとき、もう目に映る畑がすごく肥えた土なんですよ。この土を沖縄に持って行きたいなと強く思ったんですよね。それから月日が経って、 20年ぶりにNYから沖縄に帰ってきました。ちょうど復帰が終わった時期で、水島(源晃)・山田(實)・津野(力男)さんたちを中心に数名の写真家の方々と懇談し、平良孝七さん、比嘉康雄さんと僕で、沖縄タイムスが座談会を開いてくださいました。みなさんのお話を伺い沖縄の文化人や写真家が日本復帰という大きな目標を目指して長年努力して来た。そして一応、日本復帰が叶ったと同時に、達成感からちょっとエポックみたいになったんじゃないか、今まで集中した非常に大きな目標がポツンと終幕になり、本土のジャーナリストや文化人が沖縄から去っていた。方向性を失い空虚な時期に思えた。そこで写真にはもっと広い可能性があるんだということを僕は沖縄の写真家に伝えたかった。「今だ、内地の肥えた土を沖縄にも持って行くチャンスは」と考え、内地から報道写真家とは違うタイプの優れた写真家を沖縄に招いて、シンポジウムを開催するまでに漕ぎ着けたのです。それと同時に、平行して香川県の小さいな山村で国際芸術祭、青年芸術祭を企画しアメリカとヨーロッパ、韓国、日本の学生を集め、写真やら絵画、陶器、彫刻など寝起きをともにして制作するというのを20年ぐらい続けました。それがいろんな意味で一段落ついたんで、今は個人的に若い人と交流をしてから、みんながさらに元気になるようにと……。
町田:良治さん自身がとてもお元気で、いろんなところでよく見かけるんですけど(笑)。
比嘉:早く定年になったら元気になりますよ(笑)。いや、元気じゃなかったんですよ、昔はね。今の様子を高校時代の友達が聞いたらびっくりするくらい運動は全然出来なかったんです。100m走ったら、ぶっ倒れてたんです(笑)。学校で毎年、全校生徒の10km(マラソン)がありましてね。当時はね、途中で脱走したらバットで殴られてたんですよ。殴っていい時代だったんですよ。で、僕はよーいどんで、校門まで行ったら、「はい、先生お願いします」とお尻向けて(笑)。殴られて刑罰をうける。殴られたら走らなくていいからね。「僕はここでリタイアです」と。それぐらい運動できなかった。それで、還暦のときにね、何か馬鹿げたことやりたいなと。24 、5歳でアメリカに行ったときのようにね、何かやりたいなって思って、何が出来るか考えました。自転車だったら出来るかなと思って、自転車で大陸横断することにしたんですよ。それまでね、全くスポーツはやったこと無かった。大陸横断が終わってマラソン始めたのも62か3歳でした。フットワークは軽いです。でもまあ、今まで病気らしい病気はしなかったですから有り難いですよ。
町田:今やっているプロジェクトのお話をお聞かせ下さい。
比嘉:今やっているのはね、絵画の方は看護大学にあるようなシリーズを続けていますけど、写真としては沖縄の素肌みたいなものを撮っています。もうひとつのテーマとしては生命の継続というのを写真でやっています。それが、まだまだ終わってないけど、もう一段階で別の形の沖縄の素肌を撮ってみようかなと思って、それで沖縄に来てもあっちこっち周ってます。でも、そろそろ公開してもいいかなとも思っています。
町田:沖縄を隅々まで歩かれていると思います。宮古も行かれていると伺ってますが?
比嘉:あのね、宮古に限らずどこへ行ってもね、まあ、なんでもそうでしょうけど例えば、行政の上から教育を見る場合と、現場をまわって見る場合とやっぱり少しは違うと思うんですよ。僕はいろんな視点で沖縄の教育状況を見たいのです。例えば、伊平屋に行ったときに校長先生が学校全体の悩みとして、学生の学力は向上して沖縄でも標準以上になったと。ところが中学生から高校あるいは専門学校で本島に出た場合、精神的に挫ける生徒が多いそうですね。昔の中学とは違うんですよ、昔は中学で覚悟を決めて高校に進学するか百姓か漁師になるかそれしか選択がなかった。今は100パーセント進学、それで強い決意がないから挫ける人が沢山出てくる。このような事実を知ったときに、僕はいろいろ考え、土地の方々と話し会いをし、この子たちに僕が手伝えることはないかと。宮古の離島の小島で子どもたちに勇気と郷土愛(優越感)を与えるには、僕に何が出来るかと考え応援したいなと思っています。「使えるが使っていないデジタルカメラ」を集めたら80台以上集まりました。それを伊良部と来間の学校に寄付し、子どもたちの自由な発想で撮影し、世界に発信しようと、目下形になって進行形です。またそういう地域で自分の作品を作るし、学校と協力して科学と美術の異なった視線で実験教育などにも役立てばと……。微力ながら外国からの視点を沖縄の方々と活かして行ければと思っています。
町田:あらためて良治さんにとっての沖縄とはどういう存在ですか?
比嘉:あのね、沖縄ね、難しい質問ですね。そうですね。ほんとにさっき言ったように7、8年ぐらいしかいないからね、人生の十分の一ぐらいだけど、思春期、青春期を過ごした影響は大きいんですかね。僕から沖縄を引き裂くことはできないでしょう。逆に故郷は嫌だと捨て去る人もいますね。それはそれでいいのです。どちらも社会と意識的な関わりが僕にとって重要なんです。沖縄と頻繁に関わりを持つようになって来た最近、沖縄をもっと知ろうとする。そして知れば知るほど不満が膨らむ。不条理が見えて来るんですね。日本対沖縄、アメリカ対沖縄に対する不満も多いです。また僕の中で、経済的な価値観を重視する世の中にも関心(不満)が高まっていますね。こうした問題点をどのように作品に展開していくかです。沖縄に対する不満があるからクリエイティブなエネルギーが沸いて来る。だからこそ沖縄の作品が作りたくなる。今のところ沖縄は写真で表現しようと思っています。60年代に渡ったアメリカもベトナム戦争やいろいろな社会問題がありました。芸術家というのは敏感に反応しクリエイティブに展開しますね。ですから沖縄もニューヨークも僕の制作活動にとって大切な拠点といえるでしょう。話しがそれるようですが、毎年のように関西や関東から友達をたくさん連れ添って参加していた名護マラソンですが、去年は名護マラソンに参加しなかったんです。今の沖縄の社会状況で、遊んではゲラゲラ笑って楽しんでいられるかと思って出なかったんですよ。今年はこういう状況だからこそ、もっと多くの人々を交え沖縄の人と騒ぐべきなのだとも思う。このような葛藤がまた沖縄を意識するのにいいですね。
素朴さが残る沖縄、沖縄人が好きです。僕なりの行動で沖縄との関係を続けていきます。町田:ありがとうございました。